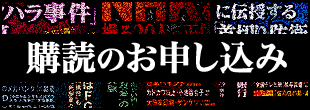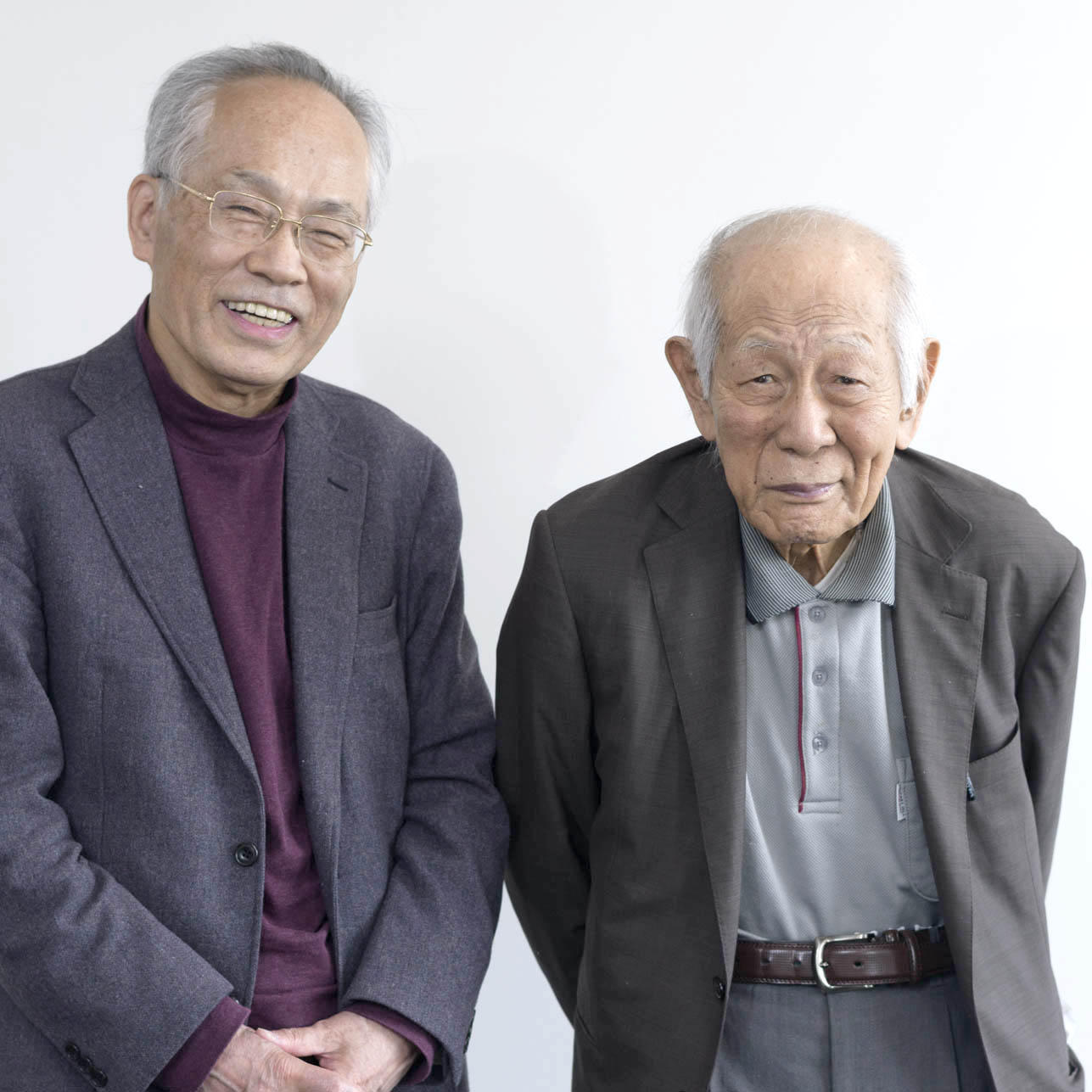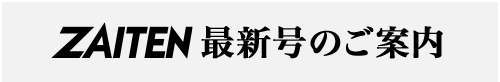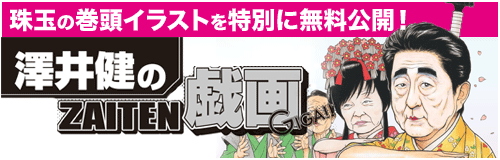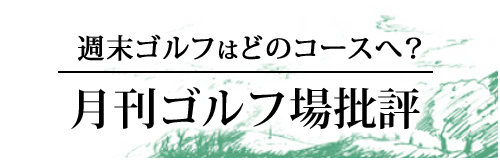2021年02月号
リモートでも“全力対応”の企業と取材からバックレる企業……
【特集・コロナ禍広報】コロナで見えた「出来る広報」「ダメな広報」
カテゴリ:TOP_free
「新型コロナウイルスの感染拡大で、取材先である企業広報の担当者も基本的にリモートワークになっています。当然、これまでのような対面のコミュニケーションは激減し、意思疎通が難しい状況が続いている。にもかかわらず、何とか取材に協力してくれようという会社もあることはありますが、大半の企業広報の対応はおざなりの傾向を強めています」
こう語るのは、全国紙の経済部デスク。
2020年年明け直後こそ中国・武漢での新型コロナ感染拡大を尻目に、日本では〝対岸の火事〟といった様相を呈していた。ところが2月に入ると、横浜港に入港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員で集団感染が発生。日本国内でも一気に危機感が高まった。そして3月には全国の小中高で臨時休校措置が取られ、4月には政府による緊急事態宣言が発令された。
企業、とりわけ大企業では緊急事態宣言に先駆けて社員の出社調整が行われ、多くが在宅勤務へと移行していった。もちろん、広報部門も例外ではなかった。前出の経済部デスクは、当時の状況を次のように振り返る。
「当初は半信半疑といった雰囲気でしたが、経済部は各社のコロナ対応を追うのに精一杯。まだ取材先の広報の間にも多少のゆとりはありましたが、それが緊急事態宣言へとレベルアップしていくに連れ、一気に非日常的な雰囲気になっていった。取材先企業と連絡が取れないといったケースも出てきて困ってしまいました」
現場の記者もあるサービス企業の取材について、こう憤る。
「緊急事態宣言の直前、直接取材が出来たまでは良かったのですが、いざ確認のために広報の直通番号に電話をかけても、まったくつながらない。仕舞いには留守番電話になってしまった」
翌日、担当者が出社して何とか連絡が取れて事なきを得たというが、別の記者は地方に本社のある大手企業を取材した際、「メールを送っても返信がなかなか来なった」と苦々しく振り返る。
「あらかじめ広報はテレワーク対応になっており、『必要なことはメールで』と言われていたので、担当者のアドレスに取材内容を送ったにもかかわらず、数日間、まったくレスポンスなし。自宅勤務っていうのは〝休暇〟のことなのかと思いましたよ」
コロナ禍でも〝好対応〟
独自性を発揮する企業広報も
一方、大手IT企業の対応には「好感を持った」と語るのは、週刊誌記者だ。
「週刊誌は新聞やテレビと違って担当がいるわけではなく、案件ごとに取材をスタートさせることになるため、どうしても代表番号に電話を入れることから始まるのですが、同社のオペレーターの対応は非常に良かった。取材趣旨を確認すると、すぐに在宅の担当者に連絡を取ってくれる。社内のインフラも含めて、円滑に対応できるようなシステムになっているようでした」
しかも、相手方にとっては決して歓迎すべき内容ではない取材だったが、「広報の中堅幹部からすぐにコールバックがあり、上席の決裁を得た上で迅速に回答を寄せてくれました」という。
やはり、業種によって対応力には差があるようで、特にIT系や通信系企業、電機メーカーなどはコロナ禍以前からリモートワークの態勢を整備してきた。あるITベンダー企業は「仮にコロナがなくても、東京五輪対応で多くの社員を在宅勤務にする予定だった」といい、コロナ禍で導入時期を少し早めただけだったようだ。いずれにせよ、企業が整備するインフラの差は大きい。
IT企業でなくとも、全社的に広報をバックアップする企業も。
「あるサービス企業は、決算期直前ということもあり、基本的に出社は経理や契約管理部門だけ。にもかかわらず、こちらが取材を入れると、即応して在宅勤務の広報につないでくれました」(経済誌記者)
また、非常時の暗い時期だからこそ、サービス精神を発揮する企業もあった。
「ある総合商社は〝絵〟になるようなイベントを積極的につくっていた印象ですね。密を避けたオリジナルの入社式を開いていたのは、その一例。こんな時期はどうしてもモノトーンなニュースが続くことになるので、アクセントをつけたイベントは記者の耳目を引いて、報道しようという気にさせる。恐らく、経営トップの発案によるものでしょう」(民放テレビ局経済部記者)
とかく横並びで批判を浴びないようにするのが大企業の発想。それを破るか破らないかは、たとえ些細なことでもあっても、経営幹部、言うなればトップの決断次第と言える。場合によっては批判覚悟でオリジナリティを発揮することが、企業のイメージアップに寄与することになる。
もっともメディアの側に、そういった需要は根強い。前出の全国紙経済部デスクが語る。
「コロナ禍でネットニュースの需要が一気に高まりました。もちろん新聞社も例外ではなく、ストレートニュースばかりではページビュー(PV)を上昇させることは出来ない。そこで、企画モノを進めようということになったのですが、その際、広報対応の良し悪しが分かれましたね」
特に業界横断的な記事の場合、同業の間でも対応の差は歴然としていたという。
「何としても社長の談話を取りたかったので、各社に文書での遣り取りも可ということで取材依頼を投げたのです。緊急事態宣言が解除になり落ち着いた時期だったこともあって、積極的にブッキングに動いてくれる広報がいる一方、まったく取り付く島もないといったところもあった。結局、担当記者の粘りで全社から談話をかき集めましたが、こういう時こそ、広報の力が問われることになると思いますね」(同)
当然ながら、「断る理由」を探ってばかりの広報に信頼感など持てるはずがない。それがコロナ禍という非常時であればなおさら。少しでも企画・記事の実現に向けて協力する姿勢を見せれば、のちのちメディア側も恩義に感じるものである。
対面とオンラインを
使い分ける広報
コロナ禍中にあって、取材対象への直接取材は〝禁忌〟と見做される傾向が強まったが、そうは言っても、〝直撃〟を避けられないのが特報を求められる週刊誌記者だ。ある契約記者は「社員編集者はリモートワークで、自分たちは現場取材を強いられる」との愚痴に加え、「コロナを理由にして、取材にまともに取り合わないようにする対象も増えた」と嘆く。
その一方、「広報からは取材を拒否されたのに、トップ本人に直撃すると、すんなりとコメントが取れた」(経済部記者)という声もあり、これも〝その人次第〟ということなのだろう。
ただ、企業が対面とオンラインを使い分けようとしている面もある。その一例がコロナ禍にあって開催された株主総会。当初、6月末(3月期決算企業)の開催が危ぶまれた株主総会だったが、フタを開けると、思いの外、すんなりと挙行された。
「配当金支払いなどのため、総会決議が必須ということはありますが、入場者数を絞ろうとしたり、質問を制限したりする動きもありました」と振り返るのは経済誌デスク。株主からの追及を少しでもかわしたい企業からすれば、コロナ禍での総会開催は出席者も激減して、むしろ「願ったり叶ったりという側面もあった」(同)ようだ。コロナ禍に伴う業績の急降下などについて、経営者による分析や見通しがどこまで株主たちに伝わったかは疑問と言える。
片や、記者会見を巡ってはオンラインの流れが強まっている。コロナ禍で経営不振に陥った企業の場合、対面で直接記者の追及を受けるよりは、モニターを介すことで、経営トップなどの心理的負担が幾分かは軽減することも確か。
「明らかに記者たちの追及のトーンは弱まっています。オンラインだと、質疑応答の間合いもどうしても弛緩したものになってしまう。そもそも、他社の記者との鍔迫り合いという会見場の熱気がなくなり、メディア間の相乗効果が発揮できなくなっています。問題を抱えた企業にとっては、有難い取材環境になっていると言えるのでしょうね」(前出の全国紙経済部記者)
また、他の記者たちからも「これまで以上に企業側がペーパーを読み上げるだけの雰囲気が強まっている」「オンラインだと、質問を重ねていくムードにならない」「元からそうだが、記者会見がさらに儀式化している」といった声が上がっている。実際、コロナ禍となって、記者会見は「オンラインに限る」と早々に決定した企業もあるという。逆に言えば、元より自身の言葉を持ち合わせていない経営者は、より発信力を弱めていくことになるだろう。
ただし、どの企業も記者との直接的な接触を避けているわけではない。コロナ第3波が訪れたこの時期にあっても、会食などを通じて積極的に記者と交流を持とうという広報もいるようだ。
「こんなご時世で飲み会を誘って来るなんて、仕事熱心な広報の明かし。好感を持ちますね」(週刊誌記者)との声がある一方、「会社からは〝不要不急の会食は原則禁止〟との通達が出ているし、会合に出席する場合は上司の許可が必要。声を掛けられても、困っちゃうんですよね」(新聞記者)という冷めた反応も。なかなかに良し悪しを断じ難い問題だが、広聴という点では、一定の評価も出来るのではないだろうか。
「記者のIT能力は低い」
企業広報の〝言い分〟
ここまではメディア側の言い分を見てきたが、当の企業側はコロナ禍中の広報対応をどのように捉えているのか。
「こちら側にまったく問題がないとは言いませんが、記者さんのITリテラシーは総じて低い」と語るのは通信会社広報。「特にベテランの記者に多いのですが、いざ、オンライン取材をするとなっても、きちんとアプリを操作できない人もいます。それでいて、部下や後輩のサポートもないようなので、会社としてどうなのかと思う」と手厳しい。
この他にも「メールの文面が雑で取材趣旨がよく分からない若手記者がいる」(建設広報)、「先方も在宅勤務なのでしょうが、レスポンスが遅い」(金融広報)、「企画モノの場合に感じますが、デスクなどとの意思疎通はうまく取れているのか」(メーカー広報)と、売り言葉に買い言葉的な記者への懸念や苦情も聞こえてくる。
さらに、「社内での取材調整も難しくなっている」という声も多数聞かれた。あるメーカー広報担当者によると、
「記者さんが地方取材をしたいというので、関係各所と調整して、何とか取材できるような状況をつくったにもかかわらず、〝東京で感染者数増加〟という報道を見た取材先の地方支社担当者が突如、〝やはり対応できなくなった〟と予定をひっくり返してくるケースも何度かありました」
結局、記者に詫びを入れるのは広報の役目。担当者の熱意だけではままならない問題も多いというわけだ。また、「〝リモートで不在なの?〟と聞かれますが、ウチは社長が毎日出社しているので、広報責任者は在宅勤務なんてハナから無理」といった別種の嘆きも聞こえてくる。
いずれにせよ、コロナ禍は広報力の向上よりは、むしろ低下させる圧力になっているというのが、本誌の印象だ。本誌の広報体験については28頁の別稿レポートに譲るが、コロナを〝嫌な取材〟から逃げる口実にしている面はやはり否定できない。また、リモートワークによって広報担当者同士のサポート体制が弱まり、勢い、担当者個人が由来のケアレスミスを発生させているケースも見受けられる。広報部門としてチームワークが発揮できないでいるのだ。
果たして、それで企業広報がポストコロナ時代に対応することは可能なのか。広報のノウハウが多分に属人的なものである以上、コロナ禍によって業務の〝伝承〟が途絶え、いざ有事が発生した際に広報がまともに機能しないということも起こりかねない。コロナ禍にあっても、広報はきちんと業務を遂行しているのか―。それを見定めることが経営者には求められているはずだ。