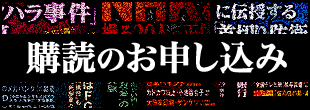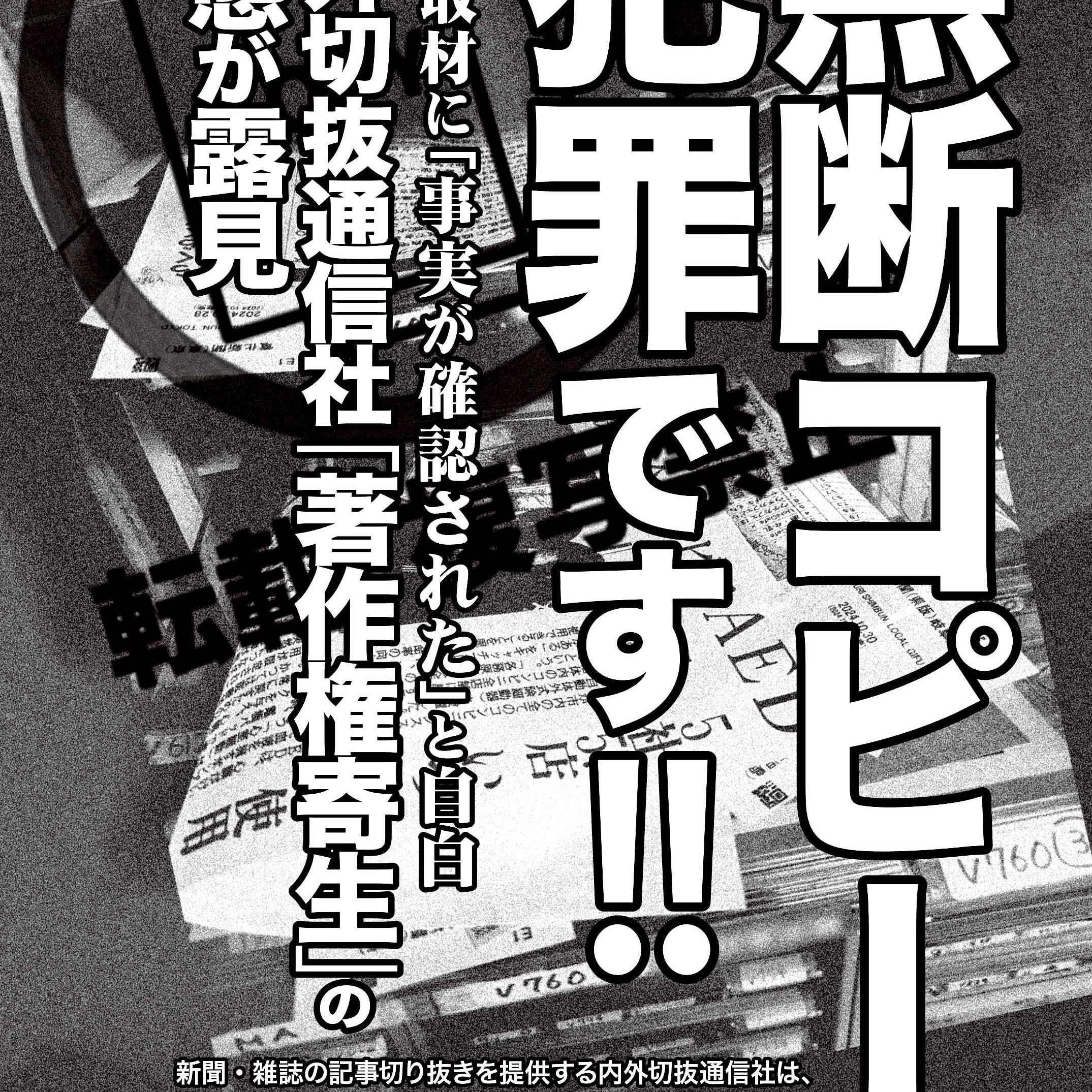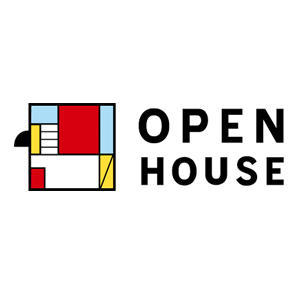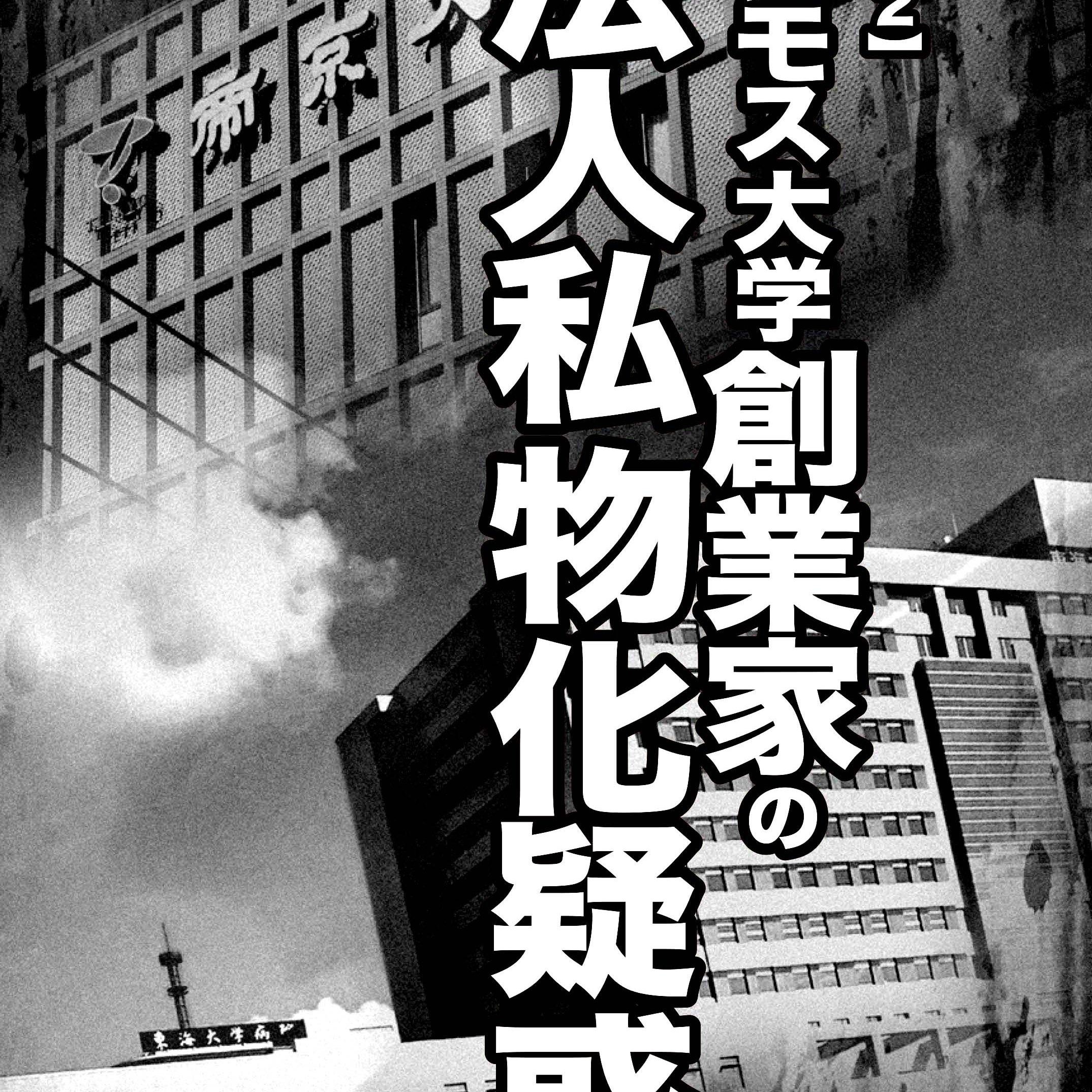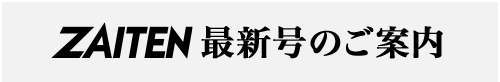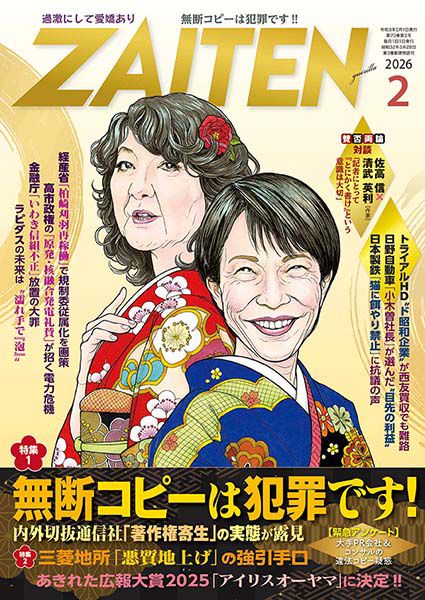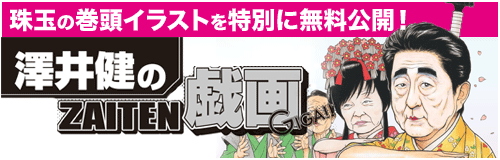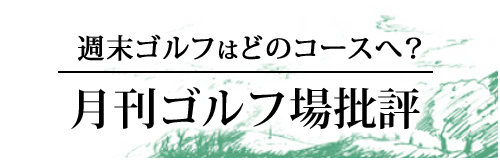ZAITEN2025年08月号
衣類から床に落ちて拡散。鼻から人体に侵入し、脳で作用する可能性―
【特集】香害問題の〝主犯〟マイクロカプセルの謎
カテゴリ:事件・社会
香害問題で、未だ解明できていないとされるのが、香りがいかにして健康被害を生み出すかという、発症のメカニズムだ。
大気中のマイクロプラスチックについて研究する早稲田大学創造理工学部の大河内博教授(環境化学)はこう語る。
「発症のしくみは、現状ではよく分かっていません。香りで苦しんでいる人たちがいて、医師の中には疾病とみなす方もいらっしゃるようですが、極めて少数。精神的なストレスであるとか、そういう問題ではないかと言われてしまう。結局、メカニズムが分かっていないので、どういう化学物質がどれくらいあったら、どういう症状が出てくるかということを明らかにしないと国としては規制できないのが現状です」
大河内教授は、過去にこの問題で厚生労働省のヒアリングを受けたことがある。担当者は香害に苦しむ人たちがいることに一定の理解を示しつつも、因果関係のエビデンスがない限り、国として対策に乗り出すのは難しいと考えている様子だったという。 「日本には因果関係を明確にしないと何もできないところがあって、欧州などとは異なります。いわゆる予防原則と言いますが、科学的な因果関係は明らかになっていないけれども、環境や人体に影響がありそうだとなれば、事前にきちっと対処しましょうというのが欧州の考え方。日本の行政も今それを見習おうとはしているようですが、実際問題としてそこまでできていません」(大河内教授)
欧州でマイクロプラスチックを使用した製品の販売を規制する動きがあることは、すでに本特集の別稿で触れた。多くの日本の環境科学系の研究者たちの間でも、基本的には予防原則を重視すべきという認識が広がっているという。 確かに、実際に症状が出て苦しんでいる人がいても、それが仮に少数ならば個人的な原因を疑うこともありうるが、一定程度の人数が苦しみを訴えている以上、何かしら共通の原因があるとみるのが自然だろう。予防原則の適用を躊躇する積極的な理由などないはずだ。
カプセル「拡散」の経路に肉薄
香害の健康被害の因果関係が明らかになっていないとはいえ、近年、新たに分かってきたこともある。大河内研究室では21年から市販の柔軟剤に使われているマイクロカプセルの計測実験を実施。この結果、実際に柔軟剤を使って洗濯をし、部屋干しした際、どれくらいの香り成分が衣類に付着し、部屋の空気中に広がっていくのか、マイクロカプセルが部屋の中のどこに飛散して残留するのかが明らかになってきたのだ。
......続きはZAITEN8月号で。