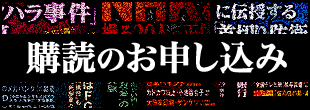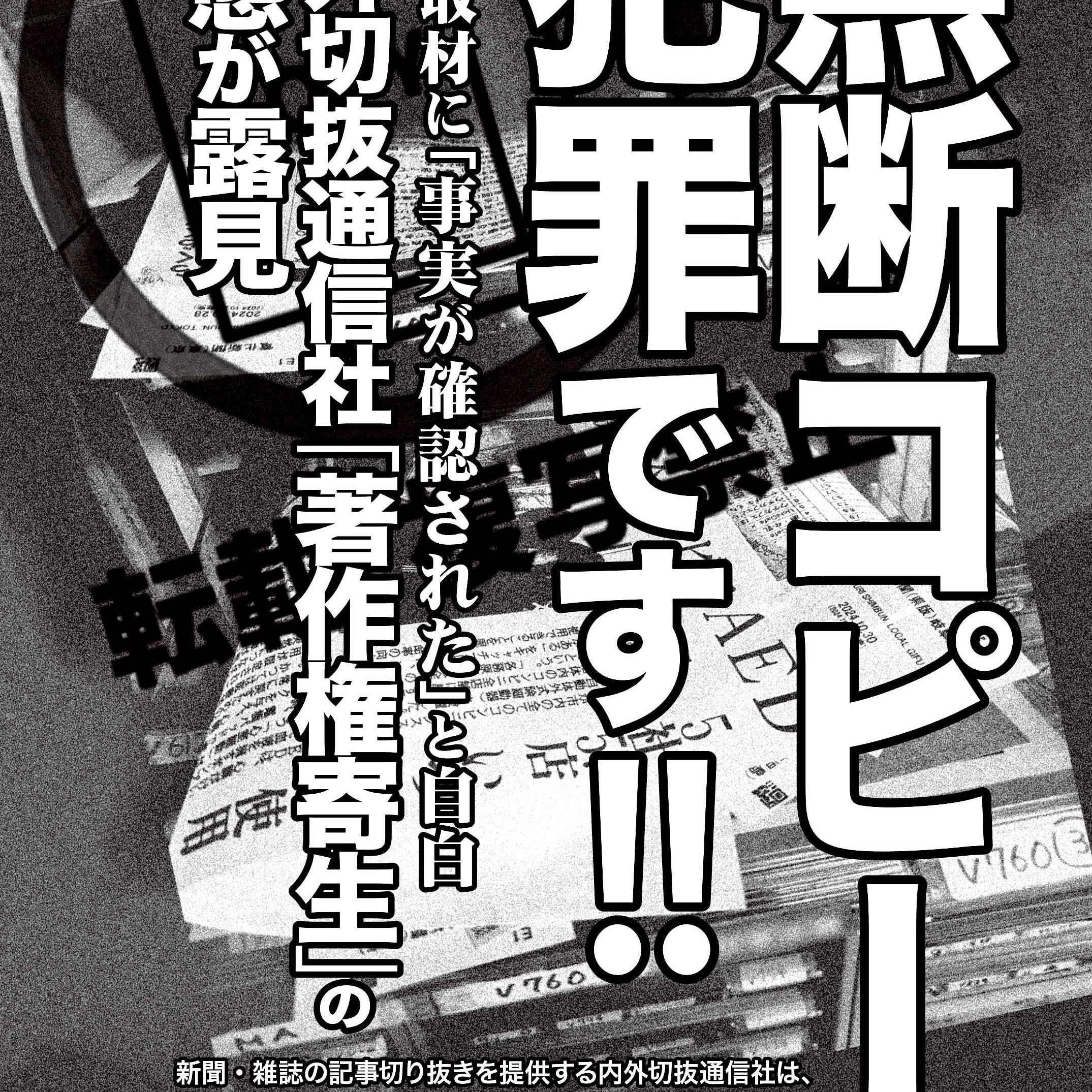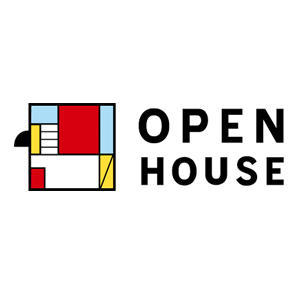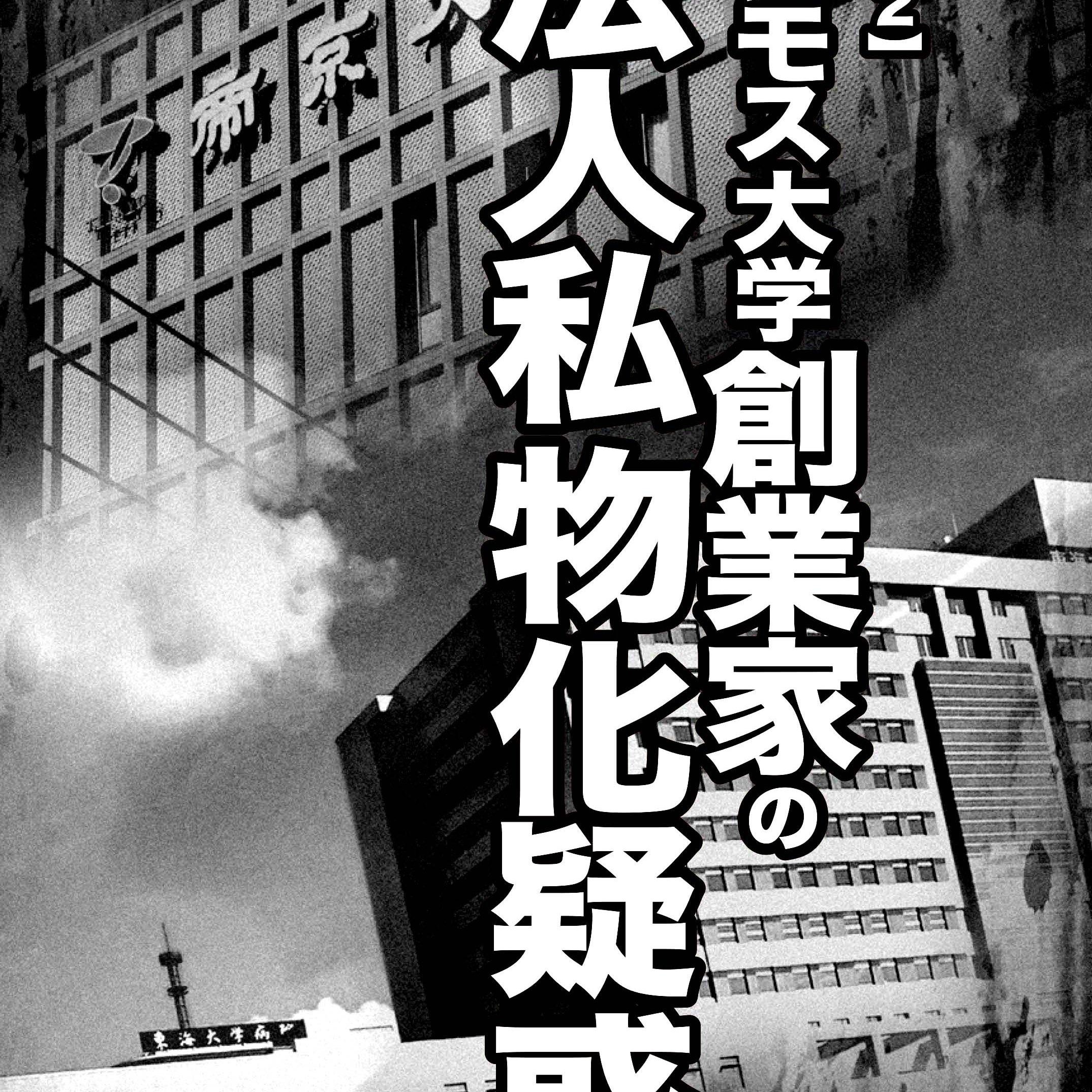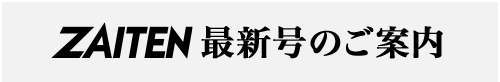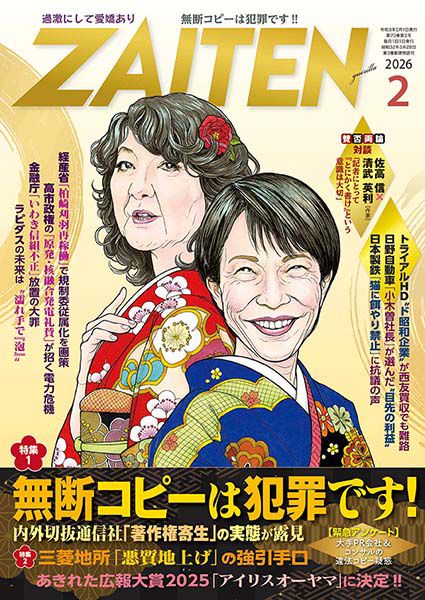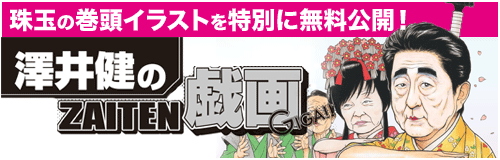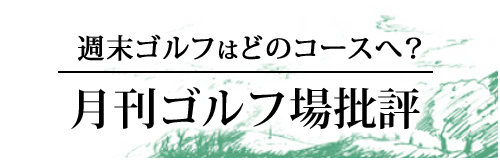ZAITEN2025年10月号
元上智大学新聞学科教授 田島泰彦
【特集】読売が「個人情報保護法」賛成に舵を切った〝Xデー〟
カテゴリ:事件・社会
「プライバシー尊重」の姿勢を強く打ち出す読売新聞とLINEヤフーだが、2社が情報の川上から川下までを掌握することで、国民の「知る権利」や「表現の自由」が侵害される恐れはないのか。
憲法・メディア法の問題に詳しい、田島泰彦氏に聞いた。
読売新聞社とLINEヤフーの共同声明を読んで思い出したのは、個人情報保護法のことです。 「プライバシー」と個人情報保護法が対象とする「個人情報」は、関係はしますが、異なるものです。従来行われてきたプライバシーの議論では、プライバシー権を重要な権利のひとつに位置づける一方、「表現の自由」や「報道の自由」など、あくまで他の基本的人権が守られることを前提にした上で擁護すべきと考え、無条件に認められる、絶対的な権利とはみなしてきませんでした。
それが1960年代の終わりから70年代にかけて、コンピューター技術の発達を背景に「自己情報のコントロール権」という概念が唱えられるようになり、特に欧州で「個人情報」、つまり氏名や住所、電話番号など、個人に関する情報を広く原則的に保護すべきとする議論と法制が進み、日本にも輸入されました。
この考え方に従うと、悪事を働く人間であれ、政治家など公共セクションを司る人間であれ、個々人の情報である限りは広くカバーし保護するべき、となってしまう危険があるため、現在もコンセンサスを得ているわけではありません。ただ、ヤフーの川辺健太郎会長が「X」に行った投稿(12頁参照)からは、この考え方の影響が強く感じられます。
また、読売新聞社が掲げる「プライバシー」にしても、個人情報保護法制定の過程を知る立場としては、危うさを感じます。
2000年代初頭に小泉純一郎政権が制定しようとしていた個人情報保護法の当初案は、個人情報を扱う上で「利用目的の制限」「適正な方法による取得」「内容の正確性の確保」「安全保護措置の実施」「透明性の確保」という5つの義務を報道機関を含むすべての事業者に課しており、これがジャーナリストや報道機関にとって死活的な「取材源の秘匿」などを困難にし、取材活動を萎縮させるとして大きな批判を浴び、当初は読売も反対していました。02年4月26日の同紙朝刊は、「報道機関が政治家の不正を取材しようとした場合、政治家の個人情報を目的外に提供した者が処罰の対象となるため、実際上、報道機関の取材が難しくなる」と書いています。
ところがこの社説が出た数日後のGW中、当時、内閣官房副長官補として個人情報保護法制定のための調整に当たっており、同年7月には公正取引委員会委員長就任が内定していた竹島一彦氏が読売新聞社を訪ね、渡辺恒雄社長(当時)に面会する、ということがありました。
......続きはZAITEN10月号で。