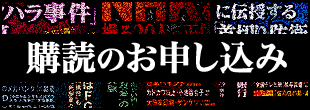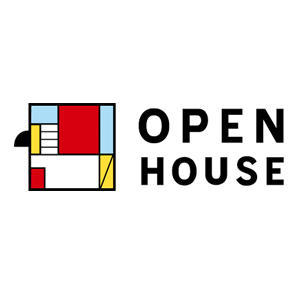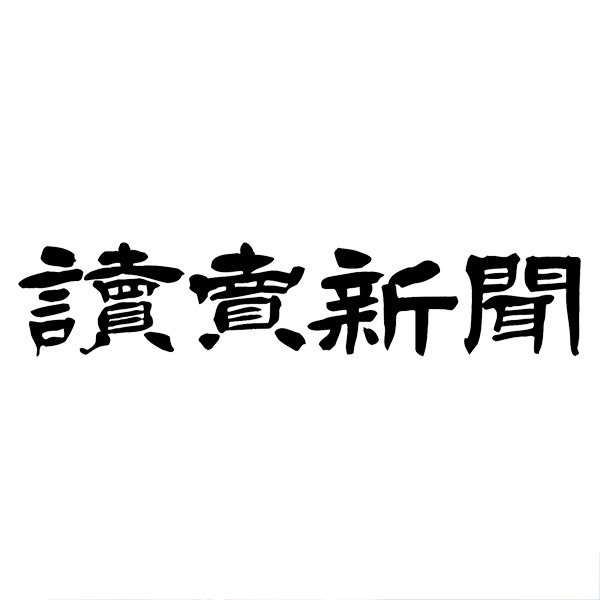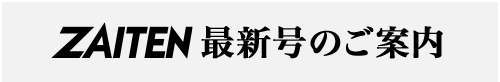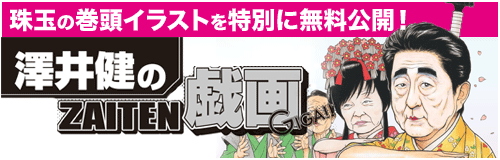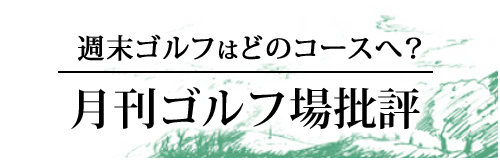ZAITEN2025年11月号
再開発は誰のため?
【特集2】ビジョンなき「タワマン乱造」の成れの果て
カテゴリ:事件・社会
日本では、人口減少が進んでいるにもかかわらず、タワーマンションの建設が続いている。 不動産経済研究所のまとめによると、2025年以降に完成を予定している超高層マンション(タワーマンション)の完成予定数は270棟、9万7141戸で、前回調査(24年3月末時点)に比べると7棟、1033戸増加している。そのうち首都圏は168棟、7万2252戸で、全国に占めるシェアは74・4%となる。
この数字の背景には、再開発事業が理由としてあげられる。
再開発ラッシュでタワマン乱造
小泉純一郎政権は、02年にバブル崩壊後の地価下落、少子高齢化や情報化の進展による社会経済情勢の変化に対応し、都市の機能の高度化や、居住環境の向上を図るため「都市再生特別措置法」を制定した。
同法には、国が指定した地域で都市再生事業を行う者が、事業のために必要な都市計画の決定や、変更(容積率の割り増しなど)を提案できるという大幅な規制緩和が盛り込まれた。
この制定を受けて、東京都では01年に「東京都の都市づくりビジョン」を策定し、「都心居住の推進」と「市街地の再開発の推進」を打ち出した。その後、「東京都の都市づくりビジョン」は「都市づくりのグランドデザイン」に改定されたが、「都心居住の推進」と「市街地の再開発の推進」の方針は大きく変えられることはなかった。
こうしたことがタワーマンション乱造にどう影響しているのか。都市開発に詳しく都市工学が専門である、埼玉大学名誉教授の岩見良太郎氏に話を聞いた。
「用途地域と呼ばれる区分により、容積率は決められており、最低で50%から1300%までの幅があります。一般的な住宅の場合は、ほとんど200%前後までに収まっています。
再開発事業で新設された建物のうち、従前の権利(土地・建物)に代え、原則等価で権利者に与えられるのが、権利床(けんりしょう)と呼ばれるものです。
対して保留床(ほりゅうしょう)は、権利床以外の部分で、売却され事業費に充てられます。
......続きはZAITEN11月号で。