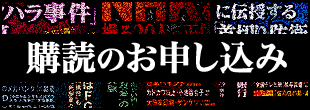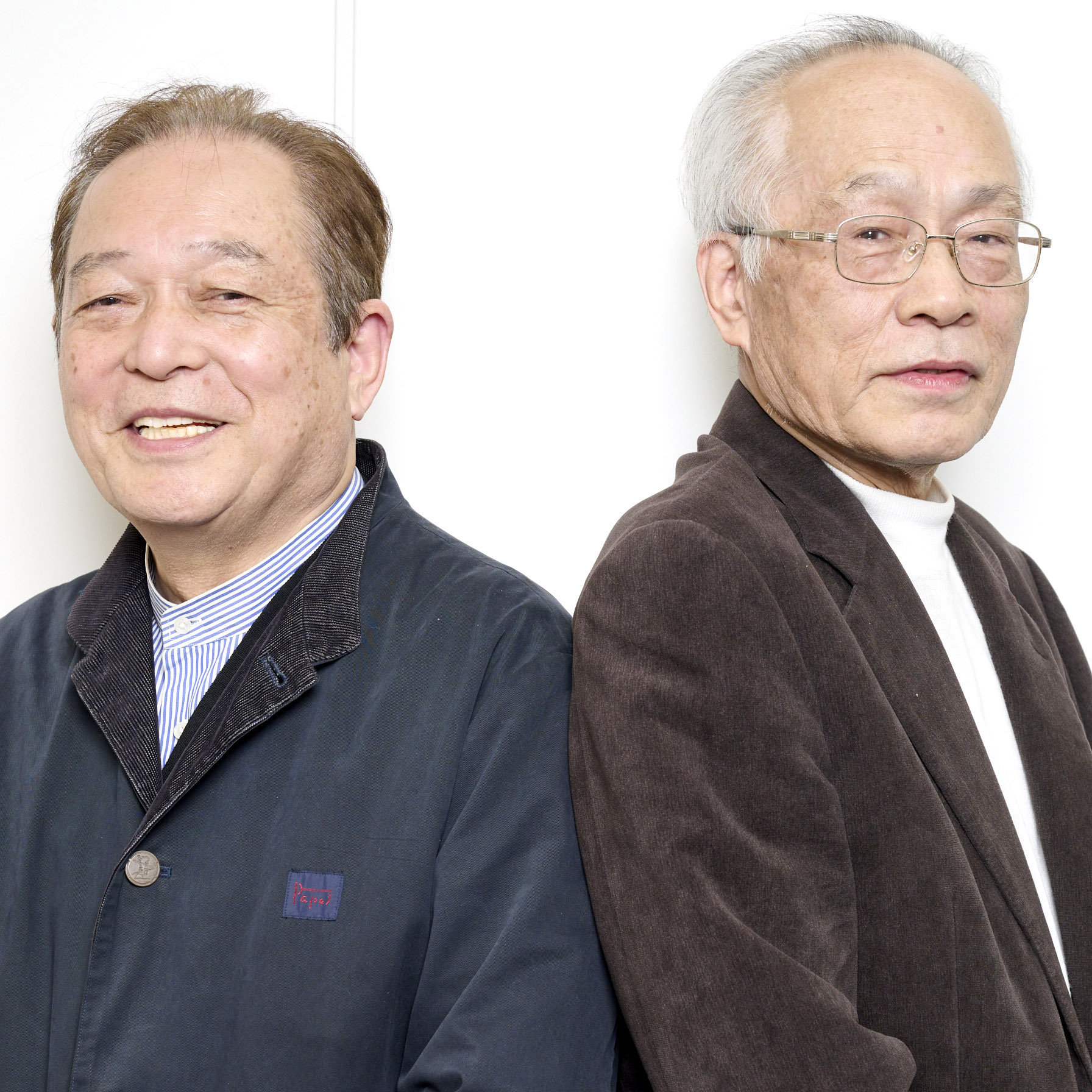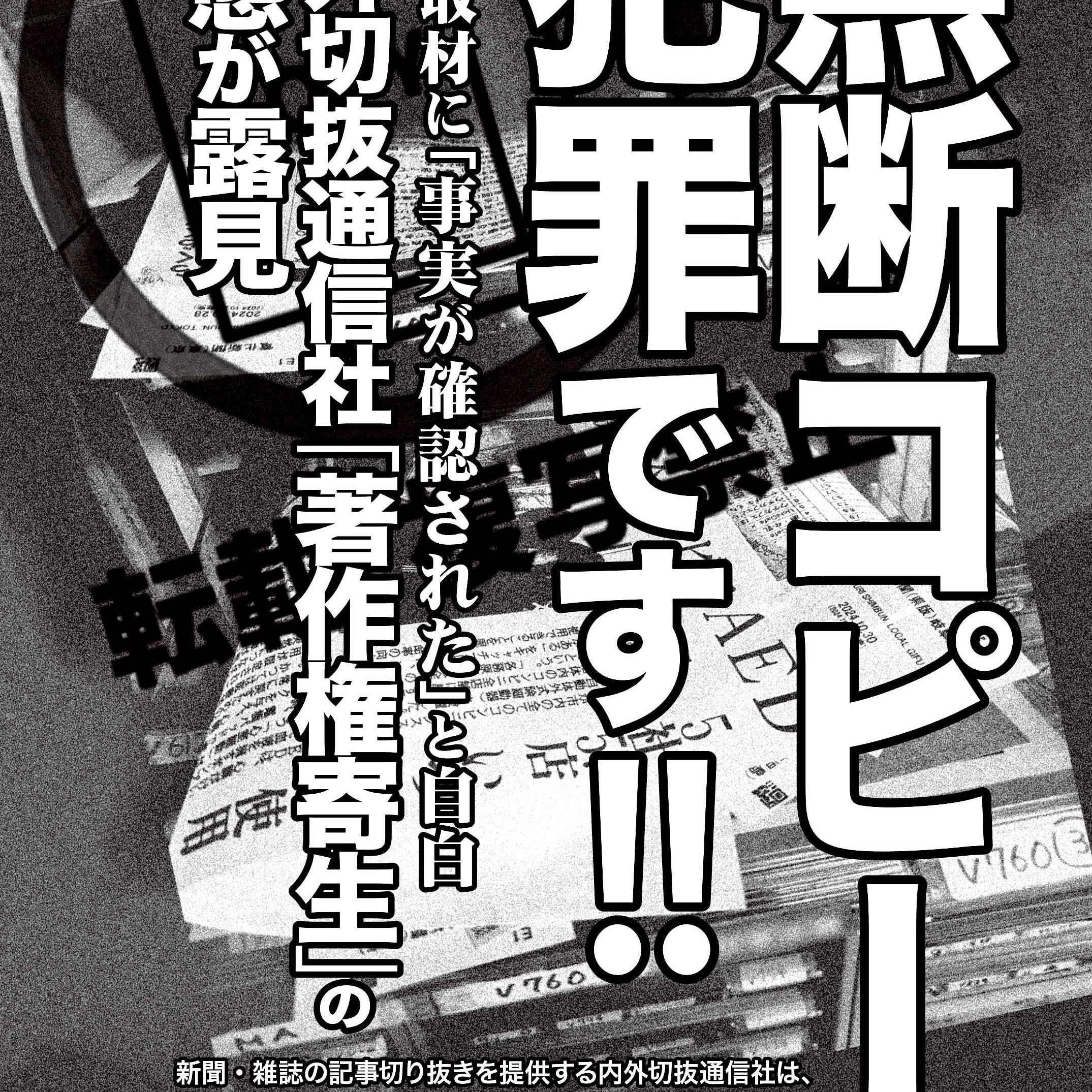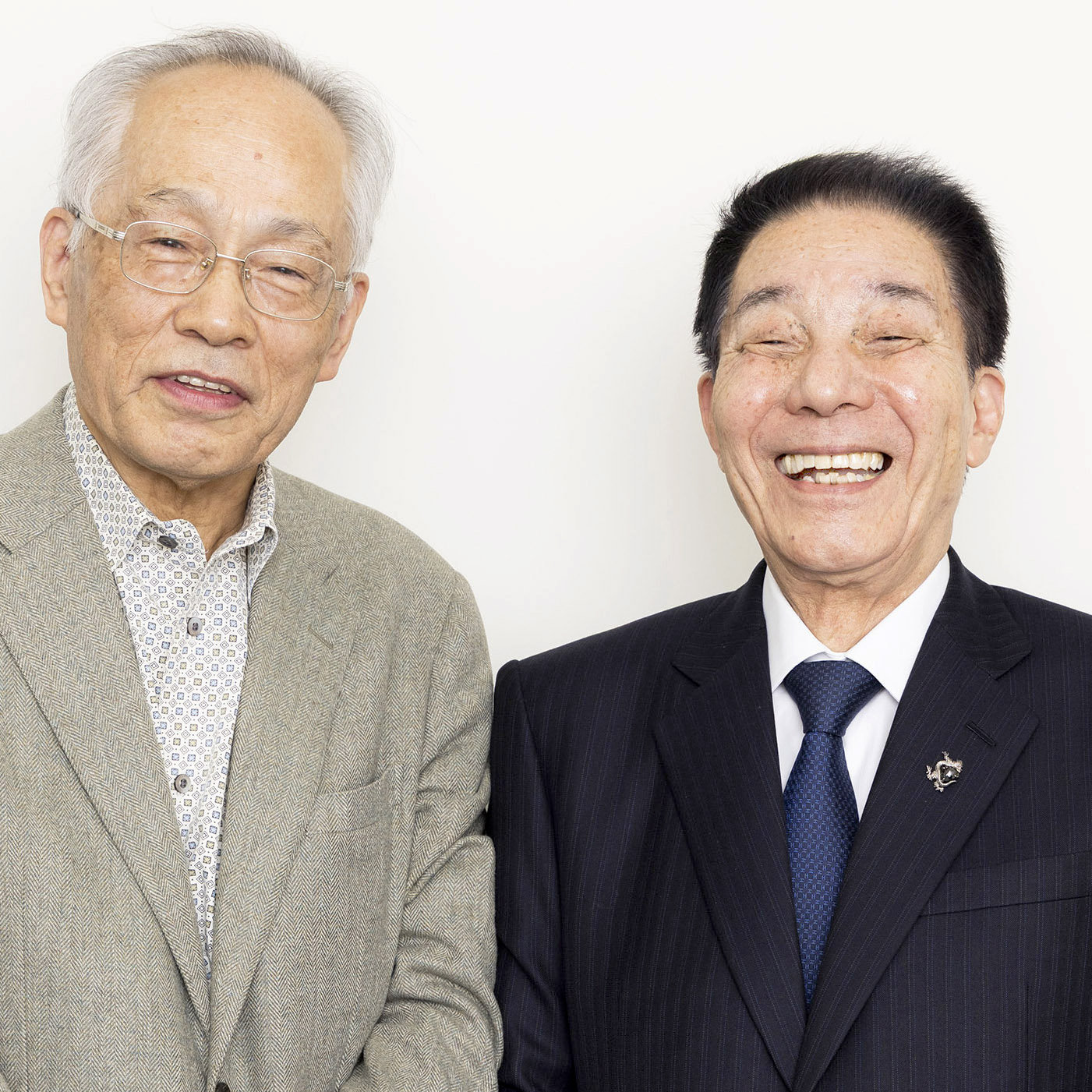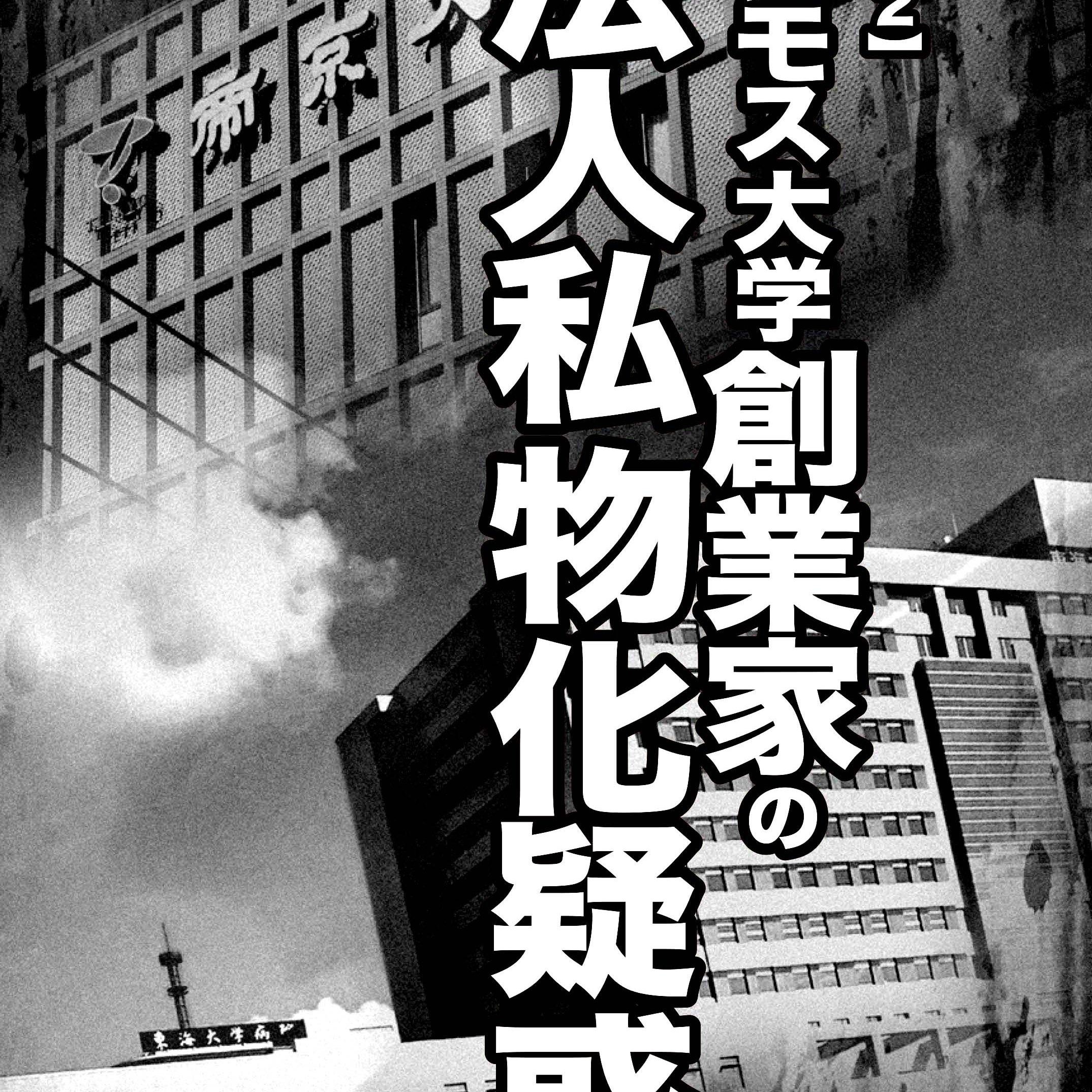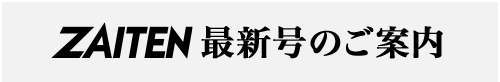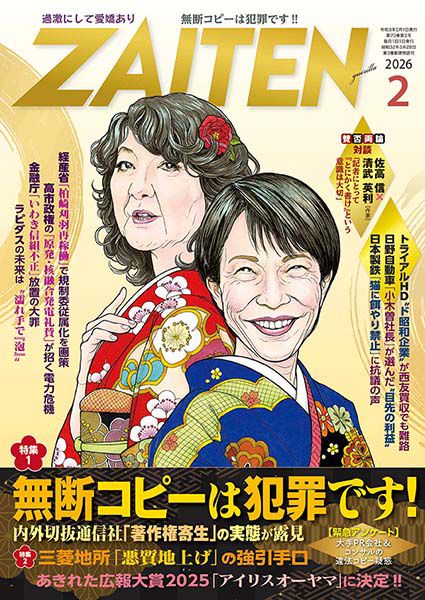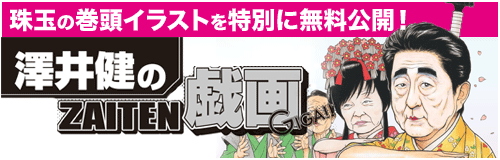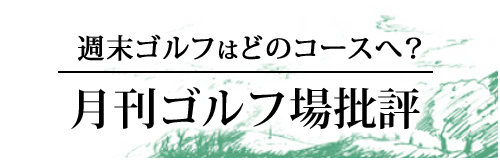ZAITEN2024年05月号
国費のムダ遣い
三菱重工「MSJさえ造れない」「H3」成功もロケット市場で惨敗必至
カテゴリ:TOP_sub
2月17日、種子島宇宙センター(鹿児島県南種子町)から打ち上げられた新型の基幹ロケット「H3」2号機は無事に目標の軌道に達した。昨年3月の初号機打ち上げ失敗から1年弱。宇宙航空研究開発機構(JAXA)のH3プロジェクトマネージャ、岡田匡史は「打ち上げは100点満点」と自画自賛した。だが、世界のロケット市場を熟知する関係者は「先頭を走る米国との打ち上げ競争は100対1の劣勢。H3は惨敗必至」と酷評する。
打ち上げ延期の歴史
日本の宇宙ロケット開発は苦難の連続だった。スタートは1954年、後に「日本の宇宙開発の父」と呼ばれる東京大学工学部教授の糸川英夫(1912〜99年)が東大生産技術研究所内に産学共同のAVSA(航空及び超音速空気力学)研究班を立ち上げた。
糸井提唱の全長23㌢のペンシルロケットから始まった国産ロケット開発は次第に本格化し、75〜82年に打ち上げられたN1ロケットは全長30㍍超の規模に拡大。この頃から構造は宇宙開発事業団(NASDA、JAXAの前身)と三菱重工業が共同開発し、機体製造は三菱重工が手がける体制が確立。ただ、86〜92年に打ち上げられたH1ロケットまでは米マグドネル・ダグラス社(97年にボーイングに吸収合併)が開発したデルタロケットの技術を導入。中核技術は機密扱いで〝ブラックボックス化〟され「国産」とは名ばかりで実質は「下請け製作」だった。
純粋に国産ロケットと呼べるようになったのは、94〜99年に打ち上げられたH2ロケットから。第1段用エンジン以下の枢要部品を全て国産化し「日本の技術力が世界に認められた」と称賛を浴びた。ところが一方で、開発途上だった91年に三菱重工名古屋誘導推進システム製作所(愛知県小牧市)でロケットエンジン部品の加圧試験中に爆発事故を起こし、23歳の同社技術者が吹き飛んだドアの直撃を受け死亡する惨事もあった。
......続きはZAITEN5月号で。